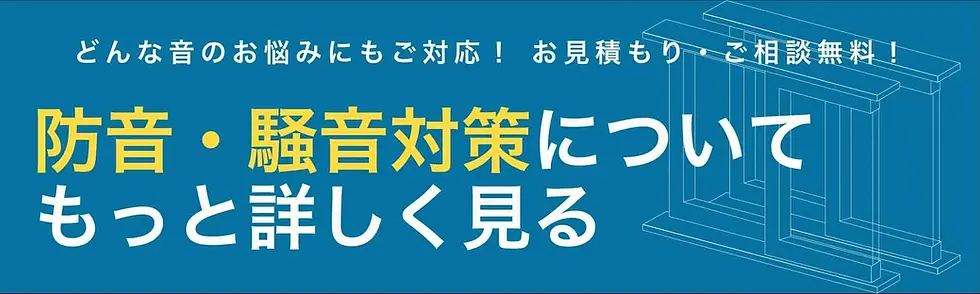〈音の基本を知る〉音の性質と人の感じ方
- riku kawanaka
- 2025年7月23日
- 読了時間: 3分
私たちの暮らしの中にあふれる「音」。その正体や、人がどのように音を感じているのかをご存じでしょうか?本記事では、音の仕組みや特徴、人の聴覚との関係について、基礎的なポイントをわかりやすく解説します。
1. 音の性質とは?
音は、空気中を伝わる「疎と密」の波、すなわち空気の密度変化によって生じます。これを音波と呼びます。

その変化によって生じる圧力の変動を「音圧(単位:Pa)」と呼びます。
また、音波には以下のような性質があります。
波長[m]:疎密の間隔
周波数[Hz]:1秒間に繰り返される疎密の回数
音速[m/s]:音が1秒間に進む距離(気温15℃で約340 m/s)
2. 可聴周波数とは?
私たちが耳で感じ取ることができる音は「可聴音」と呼ばれます。この可聴音の周波数範囲は、およそ20Hz~20,000Hz(20kHz)です。
この範囲外の音には以下のような名称があります:
超音波:20,000Hzを超える高い音
超低周波音:20Hzより低い音
低周波音(国内基準):おおむね100Hz以下の音

88鍵のピアノの場合、最低音が約27Hz 最高音が4186Hzになります。
3. 音の高さ(ピッチ)
「音の高さ」は周波数によって決まります。周波数が高いほど、高い音に聞こえ、周波数が低いほど、低い音に感じます。
つまり、「1秒間に何回空気の疎密が起きるか」が音の高さを決めているのです。

赤色と青色の波形を比べた時に赤色の方が間隔は狭いことがわかると思います。これは青色と比べて音程が高いことを表しています。
4. 音の大きさ(ラウドネス)
「音の強さ」に対する人の感じ方を音の大きさ(ラウドネス)と呼びます。この感覚は、1000Hzの音と同じ大きさに聞こえる音を基準にしたphon(フォン)という単位で表されます。
等ラウドネス曲線(ISO 226:2003)
等ラウドネス曲線とは、同じ大きさに聞こえる音を周波数ごとにプロットしたものです。
音が小さいとき:低い周波数ほど感度が下がり、大きな音圧が必要になる
音が大きいとき:周波数にかかわらず平坦に感じる
最も感度が良い周波数:約4000Hz付近
聴こえる音の限界
最小可聴値:人がかろうじて聴き取れる音の下限(周波数によって変わる)
最大可聴値:約130dB程度。これを超えると痛みや不快感を伴い、やがて音として知覚できなくなります。
5. マスキング効果とは?
マスキングとは、ある音が存在することで、他の小さな音が聞こえにくくなる現象です。
たとえば
深夜に静かな部屋で、日中は気づかなかった時計の音が聞こえる
騒がしい場所で携帯電話の着信音が聞こえづらい
これは、背景の音が他の音を“覆い隠す”ことで、聴こえるはずの音の最小可聴値が上昇するからです。これをマスキング効果といいます。
まとめ
音の性質や人の聴覚は、私たちの生活環境や音響設計に深く関係しています。「ただ聞こえる」だけではなく、「どのように聞こえるか」によって快適性や集中力も大きく左右されます。