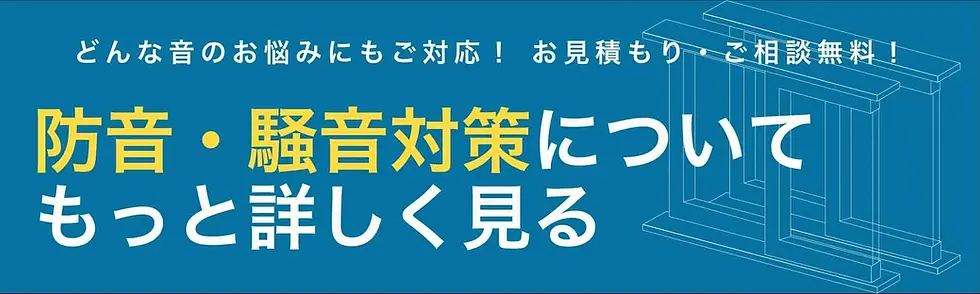壁、薄すぎませんか?オフィスの「音ストレス」が集中力を奪う
- riku kawanaka
- 2025年5月21日
- 読了時間: 3分
1. オフィスに潜む“音ストレス”とは?
オフィス環境における快適性の多くは、視覚や温度といった要素に目が向きがちですが、意外と見落とされがちなのが「音」の問題です。特に近年、オープンオフィスやガラス張りの会議室など、デザイン性を重視した空間が増えたことで、「音が漏れる」「周囲の声が気になる」といった“音ストレス”を訴える声が多くなっています。
2. 壁の“薄さ”がもたらす問題点
会議室の壁や仕切りが薄かったり、防音性能が不十分な場合、会議中の会話や電話の声がオフィススペースに筒抜けになります。特に社内会議で使われる専門用語や個人名、案件名などがはっきり聞こえてしまうと、業務に関係ない人にも意図せず情報が伝わってしまい、集中力を大きく削がれる原因になります。
また、守秘性が求められる内容が漏れ聞こえることで、セキュリティ面でのリスクも否めません。
3. よくあるシチュエーションと従業員の声
実際の現場では、次のような声がよく聞かれます。
「隣の会議室から笑い声がずっと聞こえてきて、資料作成に集中できなかった」
「静かな空間なのに、重要な打ち合わせの内容が全部聞こえてきて気まずい」
このような状態が日常化すると、「気が散る」以上の問題になります。
4.実際にあったケース
実際に弊社にご相談があったケースを元に、対策をご紹介しております。
画像右下の会議室での声が、画像左側のオフィススペースに聞こえてしまい、業務に集中できないというご相談内容でした。
現場調査の結果、音が伝わってしまう原因は大きく分けて3つの原因がありました。

1.建具(ドア)が遮音性能をほとんど持たないため、音がそのまま抜けてしまう。
2.間仕切り壁の遮音が不十分で音が伝わってしまう。
3.天井面の遮音が不十分で音が伝わってしまう。

音の問題を語る際には音を出す側を「騒音側」音を受け取る側を「受音側」といいます。
音問題が発生した場合には「受音側」で音を止めることがコストパフォーマンスの高い対策に繋がります。この場合ですと画像右側の会議室側にあたります。
5.弊社の方からご提案した対策
1.建具(ドア)が遮音性能をほとんど持たないため、音がそのまま抜けてしまう。
→会議室のドアを遮音できるものに変更します。
こちらの扉はほとんど遮音性能をもっておらず推定で「TS-15」という遮音性能でした。簡単にいうと、このドアで15dB減衰する遮音性能という意味です。
こちらはT-3 (35dB減衰する)ドアに変更し、弱点となっているドアの部分をしっかりと遮音します。
2.間仕切り壁の遮音が不十分で音が伝わってしまう。
→非常に簡易的な間仕切り壁の遮音性能を引き上げます。壁の遮音性能を上げる方法は大きく分けて3つあります。
・壁を厚くする(部屋内側に新たに壁を立てる)
・壁の密度を高くする(壁面内部にGWを充填し、石膏ボードを重ね貼りする)
・上記2つを組み合わせる
今回のケースでは壁面を一度解体し、グラスウールを充填後、石膏ボードを重ね貼りすることで遮音することになりました。
3.天井面の遮音が不十分で音が伝わってしまう。
→システム天井というユニット化されている部材を使用するタイプの天井でしたが、照明や設備の寸法が合わず、あちこちに隙間が空いている状況でした。
こちらの天井は一度解体し、遮音天井を施工します。
6.対策の効果は?
弊社は部分的な部分的な防音や防音室の設計時にも「騒音計算」「遮音計算」を実施します。これは簡単にいうと、騒音源で発生した音がどのような経路でどの程度伝わるかを計算したり、遮音工事後にどの程度、効果が得られるかを計算にて出すということです。
今回は会議室で発生した音が、オフィススペースでは「音はなんとなく聞こえるが内容は分からない」という遮音性能を狙い、予測計算通りの施工となりました。